
こんにちは。
墨絵師のベベ・ロッカです。
シクラメンの花をご存知ですか?
別名、「篝火」「豚の饅頭」とも言います。

ぶ、豚さん・・・???
そう、その名前の秘密は、最後に明かされますよ。
シクラメンは、初冬から春にかけての寒い時期に咲く花。
鮮やかな色とそっくり返った形がとても個性的で、人気の花でもあります。
水墨画でもよく描かれるテーマなんです。

今回は、シクラメンの花の描き方を詳しく、解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください!
目次
シクラメンの描き方を「動画」で見る
シクラメンの描き方を、まずは動画で見てみましょう。
2分23秒の短い動画で、解説はなく音が鳴ります。
水墨画で簡単に描くシクラメン「花」
それでは、動画をもとに順に解説をしていきます。
使用しているのは、こちらの顔彩の色です。
【使用する色】
・花・・洋紅(赤色)
シクラメンの花弁は基本5枚ですが、花のつき方が独特なので、5枚全部をキッチリ描く必要はないですよ。
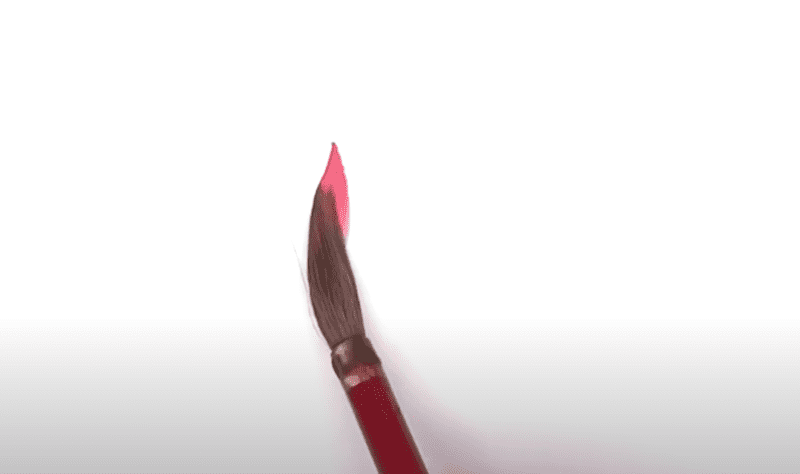
では、1枚目。
手前の花びらから。
色を穂先に取り、筆を紙に置き、置いた状態のまま少し引きます。
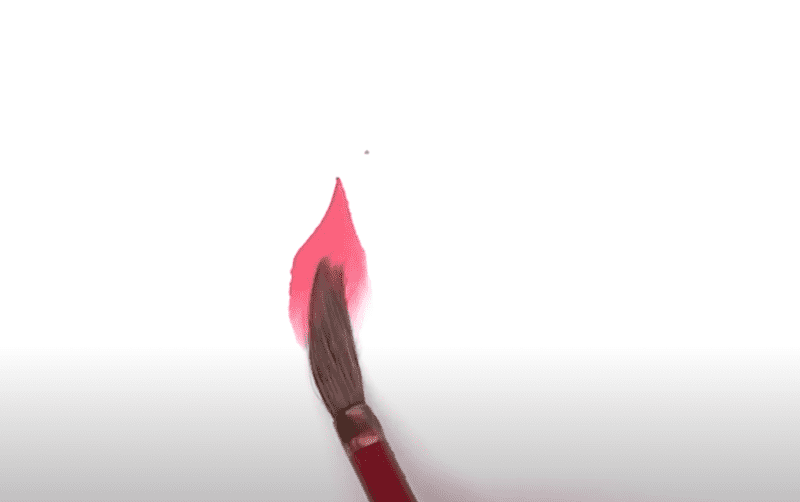
2筆めも花のふくらみを作るように、1筆目のややとなりにそっと置きます。
1・2と、これで1枚の花びらの完成です。
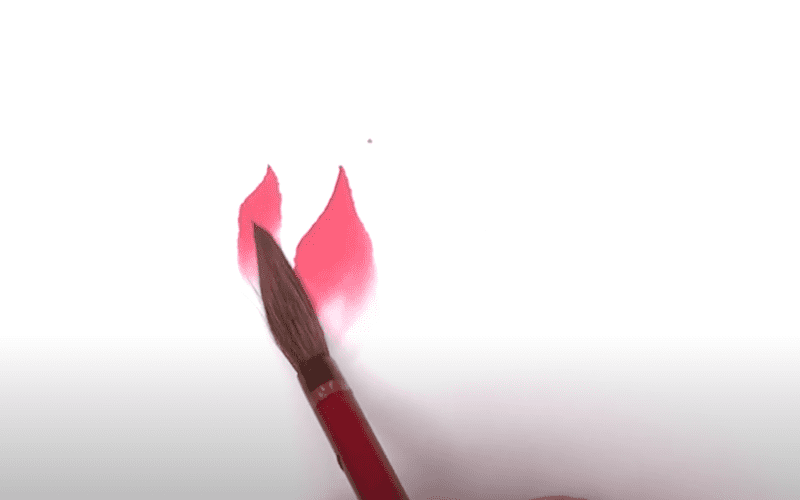
2枚目の花びらです。
次は横向きになっているので、先ほどより細めに描きます。
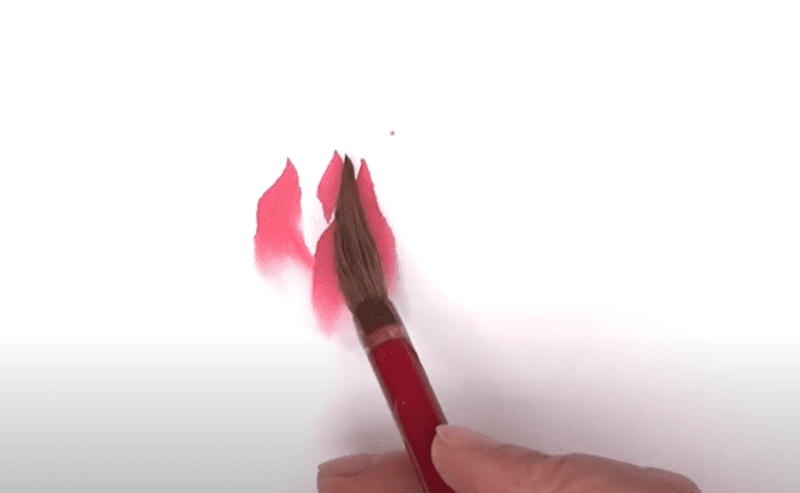
3枚め。
さらに向こう側になるので、小さく見えます。
筆の穂先をちょんと軽く置きます。

4枚め。
右側に細く描きますが、左側とは少し形を変えて、変化をつけます。
これで花びらの部分は完成。
花びらの先端と根元の濃淡を出すのがポイントです。
濃淡を出すためには、筆の穂先だけで描くのではなく、筆を置いたらそのまま腹を使って引くようにすること。
頑張ってみてください。
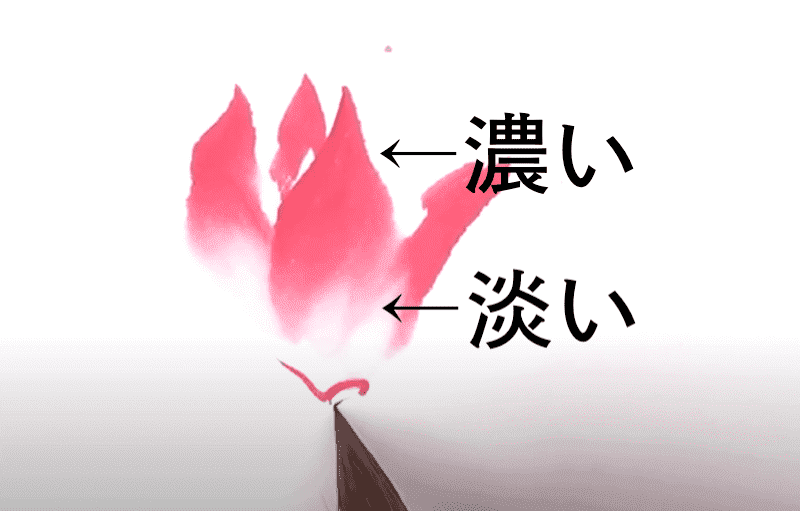
こんなふうに濃淡を出すには、あらかじめ筆に仕込んでおくことが秘訣なのです。
水墨画では基本とされている技法に、「三墨法」があります。
濃・中・淡の3種類の濃さの墨をそれぞれあらかじめ皿に作っておきます。
それを順番に筆で取っていくと、筆の中にこんな層ができてそれを利用して、紙の上に濃淡を作る、というものです。
でも!

ここまで、細かく層を作る必要はありません。
べべ・ロッカ流では、もっと簡単に濃淡を作ります。
①まずきれいに筆を水で洗う(墨や色が少しでも残っていたらダメ)
②濃いめの墨や色を筆の穂先に取る
③皿の上で調墨する(調墨とは、筆を皿の上でゴニョゴニョとなじませることです)
以上。
3段階の濃さを作って、3回も取る必要はありません。
大切なのは、筆の腹を使うことです!
やってみてください。
次はひっくり返りの口の部分です。
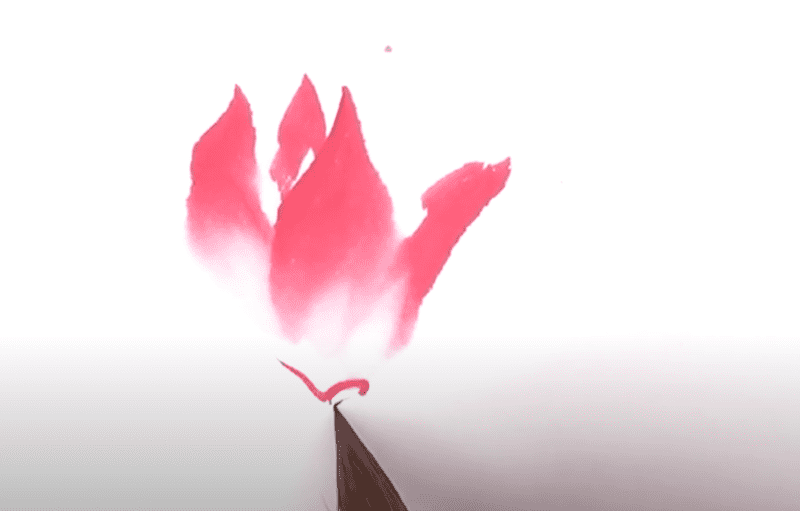
筆の穂先を使って、小さな口を描きます。
次にもう1つの花も描いてみましょう。

1枚めの手前に見える花びらは、先ほどと同じように2筆で。
筆を2回使って1枚の花びらを作ります。
まず1筆め。
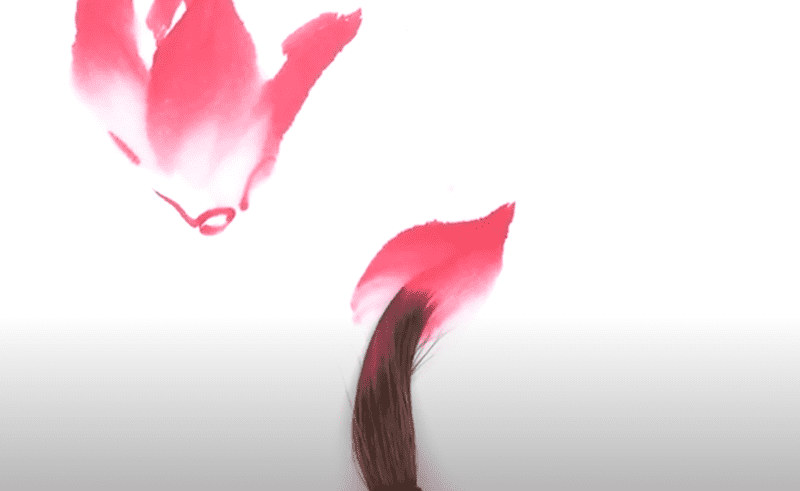
そして2筆め。
これで1枚の花びらができます。
1枚めの花びらだけ2回で描くのは、手前にある花びらなのでやや大きめに描くためです。
全ての花びらが同じ、というのは不自然ですから、1枚ずつ少しずつ変化を持たせるためなのですね。

2枚めは小さめにちょん、と筆の穂先を置きます。
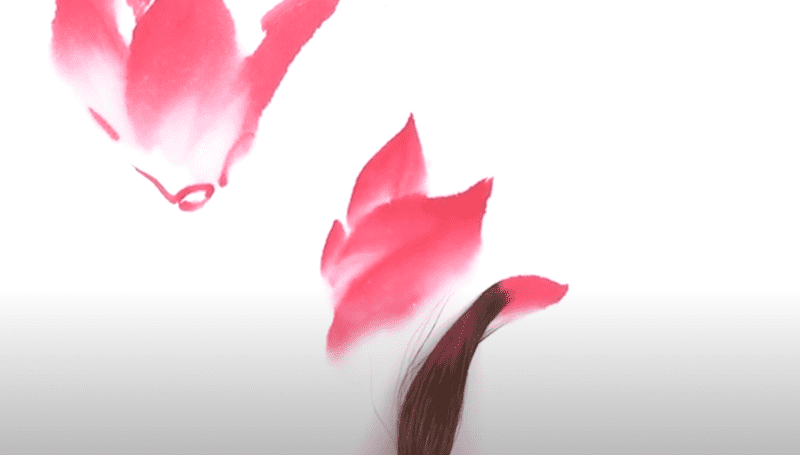
3枚め。

4枚め。さらにちっちゃく。
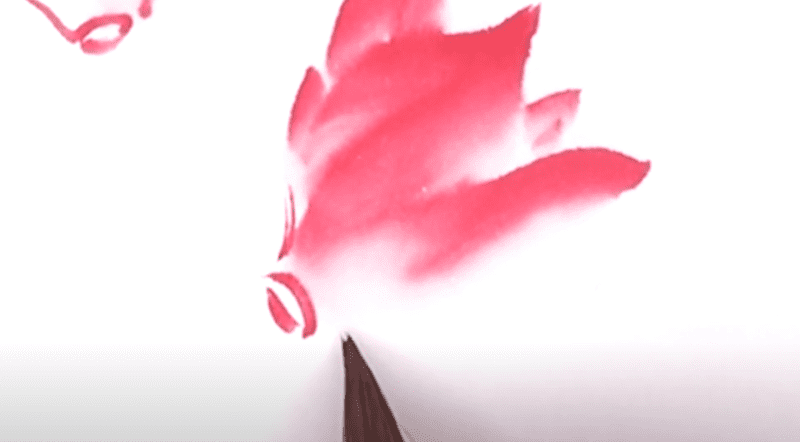
こちらも、口の部分を描いたらこれで花は完成です!
次は、茎を描きます。
水墨画で簡単に描くシクラメン「茎」
【使用する色】
茎・・・墨
もし、色を使う場合は、茎の色は「煤竹」(こげ茶色)がベストです。
茎に「煤竹」を使うなら、葉も色を使った方がバランスよく仕上がります。
その場合は「濃草」(濃い緑色)が相性がよいですよ。
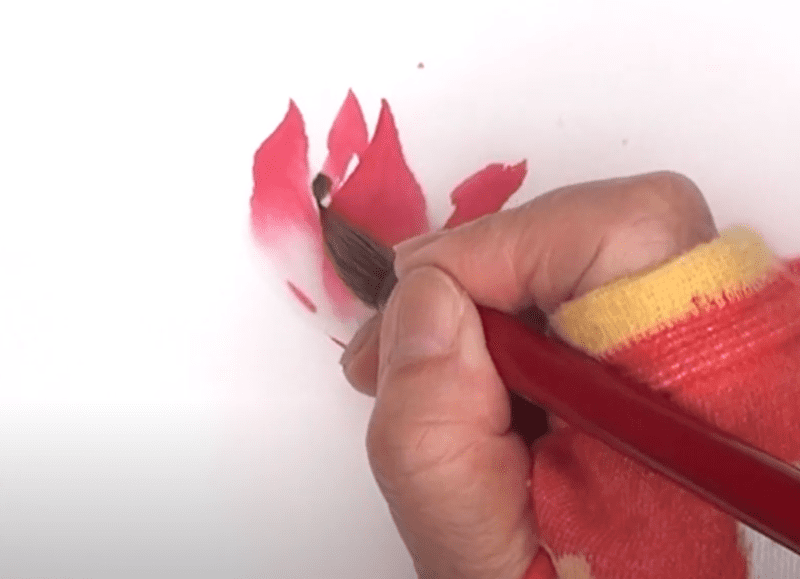
花びらの隙間にほんの少し、茎の一部を描きます。
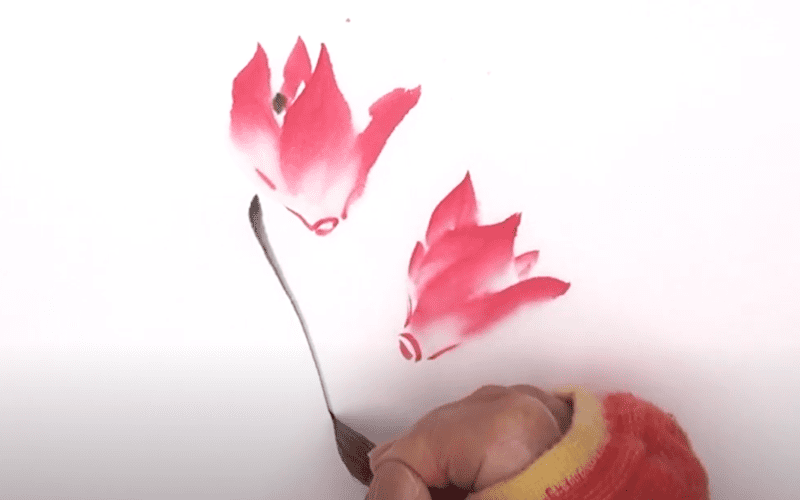
筆を直筆でスッと引き、茎を仕上げます。

もうひとつの花も同様に。
茎が出来ました。
次は、つぼみです。
筆の使い方についての詳しい解説はこちら↓
水墨画で簡単に描くシクラメン「つぼみ」
【使用する色】
つぼみ・・・洋紅
茎・・・墨(色を使う場合は「煤竹」がおすすめです)
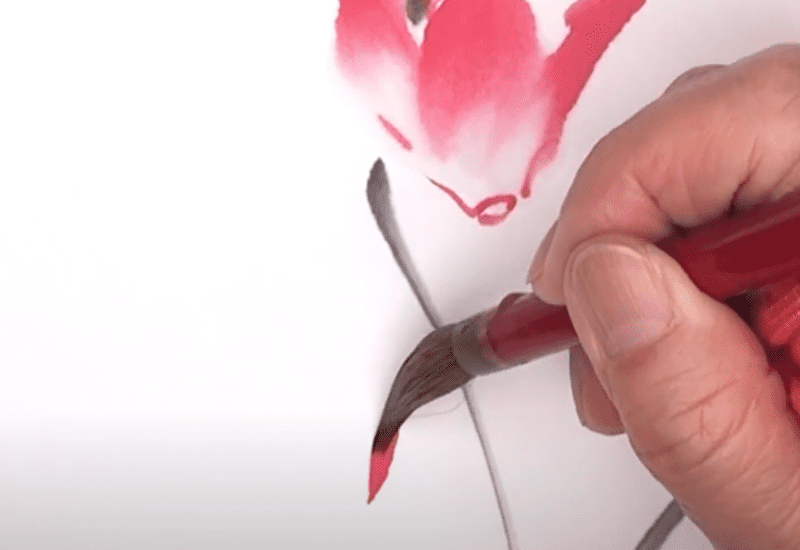
シクラメンのつぼみはほっそりしています。
筆の穂先を下に向けて、スッと上方向に移動します。
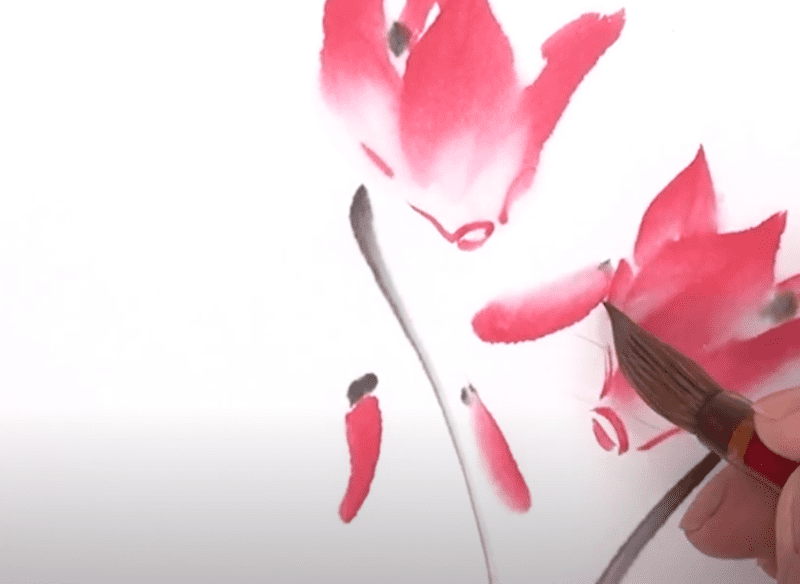
角度や向きを少し変えながら、つぼみをいくつか描きます。
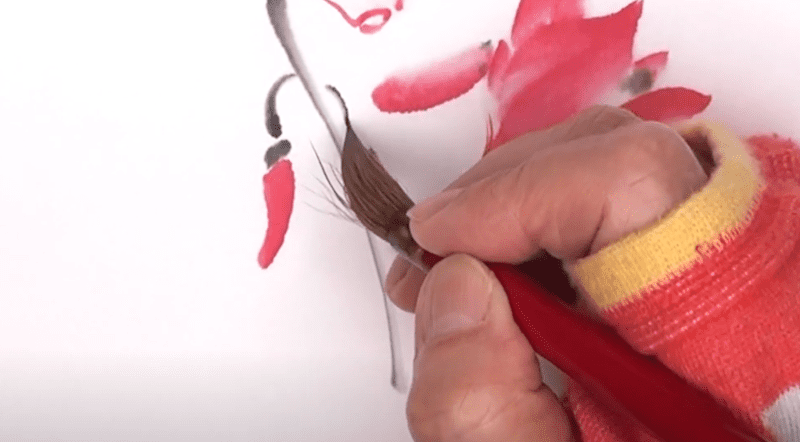
つぼみは、お辞儀をするようにクルンとカーブして下を向いています。
茎は丸みをつけてクルンと弧を描き、スッと下に引きます。

つぼみの茎は丸くカーブをつけるのが大切です!
茎をスッとまとめたら、最後は葉っぱです。
水墨画で簡単に描くシクラメン「葉」
シクラメンの葉は、茎の根元にこんもりと覆いかぶさるように集合しています。
向きを少しずつ変えながら葉を密集させて描きます。
【使用する色】
葉・・・墨(色で描く場合は、「濃草」がおすすめです)

茎の根元が集まっているところあたりに、葉を描いていきます。
葉はハートのような丸みのある形ですが、ナナメから見た構図なので、やや楕円形に描くとバランスが良いです。
筆を横にして、筆の腹も使いながら描きます。

1筆では描けないので、筆の腹を使いつつ葉っぱ全体の形になるように運筆します。
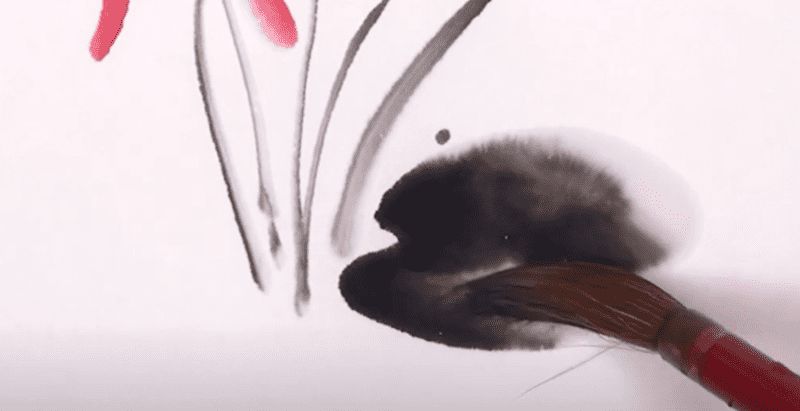
ハートっぽい形なので、少し「欠け」を作るとベスト。

次は正面の葉です。
こちらも筆の腹を使うようにして描きます。

少し形を変えながら違う葉も描きます。

向こう側にも葉はありますよね。
ちらりと見える程度でOK!

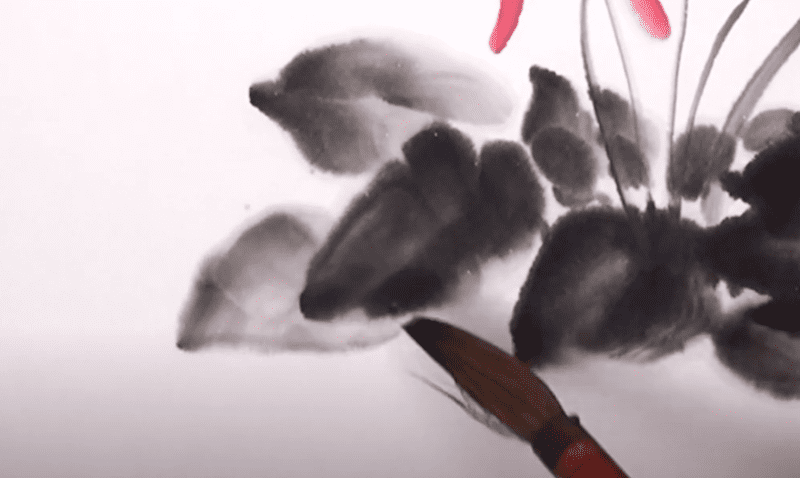

最後に、葉の葉脈を描いたら、完成です。
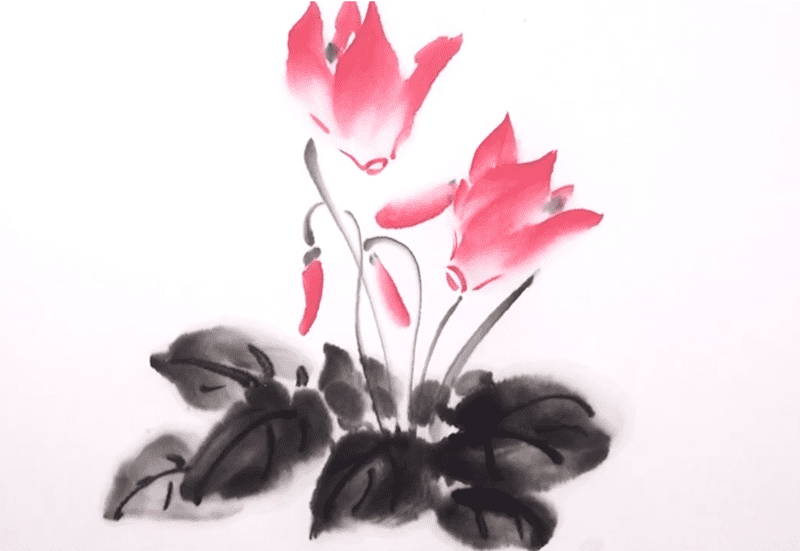
シクラメンってどんな花?

シクラメンは、サクラソウ科の多年草です。
色は赤・ピンク・白など可愛らしく鮮やかで、冬の寒い時期に咲く花として人気ですね。
サクラソウ科といっても、サクラソウとは全然違う形です。
初めはつぼみは下を向いていて、日に日に花びらが開いていき、よいしょ!とひっくり返るのです。

面白いですね。
花の咲き方が似た種類では、「片栗の花」があります。

カタクリの動画もありますよ!↓
(1分45秒 音が鳴ります♪)
シクラメンは、地中海沿岸地方が原産で、日本へは明治末期に渡来しました。

別名を、「篝火」「豚の饅頭」と言うそうです。
「篝火」・・・シクラメンの花はとても個性的で、そっくり返るような形が特徴です。
その様子を見た明治時代のある貴婦人が、「篝火のよう」と表現しました。

その後、植物学者の牧野富太郎によって「篝火花」と名付けられました。
とても美しい名前ですね。
思いついた貴婦人のセンスには脱帽です。
一方・・・・
なんで豚さん??
どこがお饅頭??
と言うのも・・
シクラメンの原産地のトルコやイスラエルでは、野生の豚がシクラメンの球根を餌がわりに食べていたそうです。
元々、英語ではシクラメンのことを「sow bread」(雌豚のパン)と読んでいたらしく、それが日本にやってきてパンが饅頭に変わったのだとか・・・・

名前の由来って「なんで???」ということはよくありますが、これはもうセンスというかなんというか・・・・・
豚さんにもお饅頭にもなんの罪はありません。
ただ、
「篝火」と名付けてくれた学者先生、ありがとう。
まとめ
今回はシクラメンの描き方を紹介しました。
冬を代表するシクラメンは、水墨画にぴったりの華麗な花です。
ポイントとしては、
・花の濃淡をつけること(筆の腹を使う)
・そっくり返っていることを意識して、茎の丸みをつけること
・葉はハート型を意識して
などです。
とても可愛いので、ぜひ描いてみてくださいね。
それでは、また。


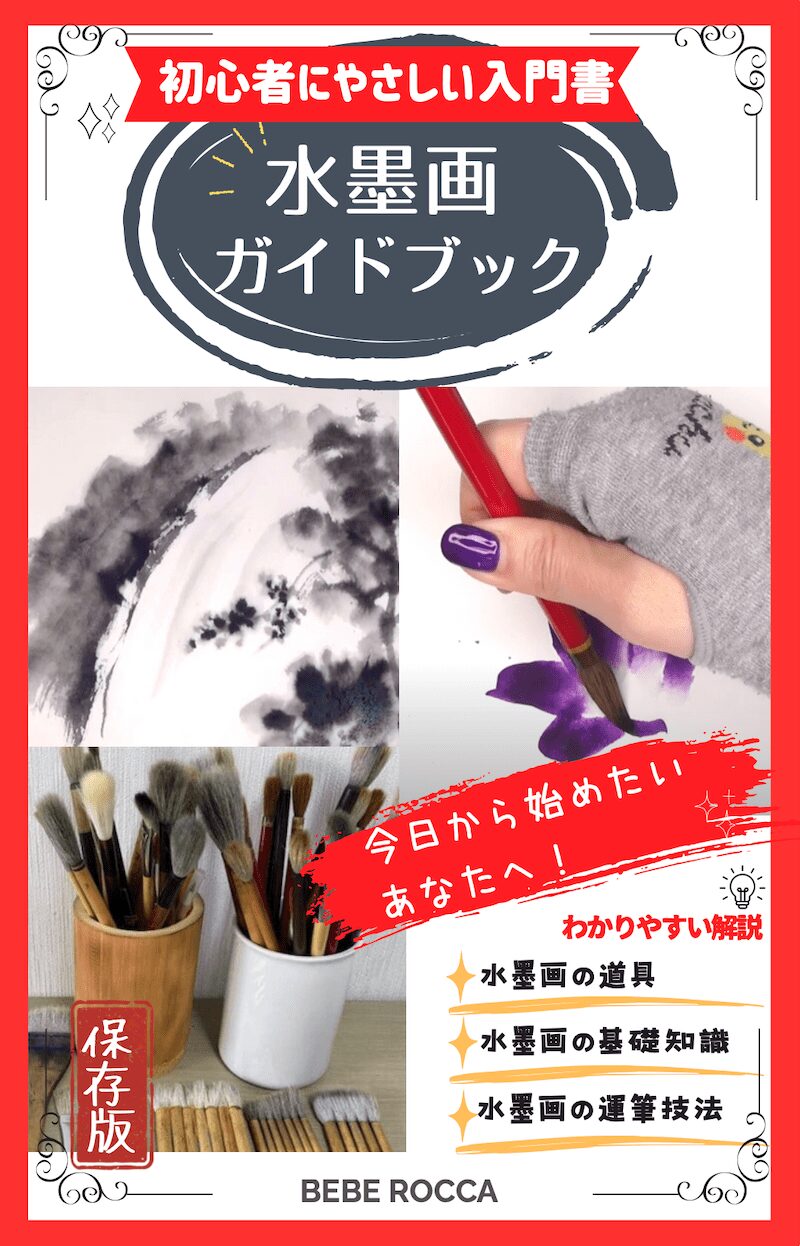









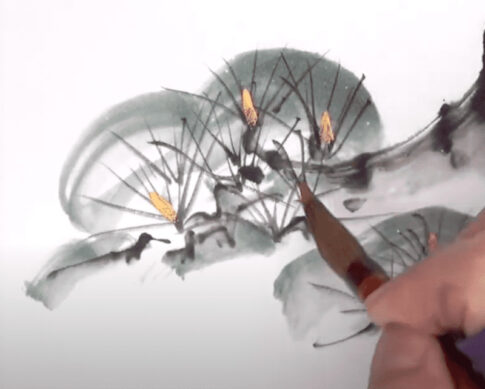
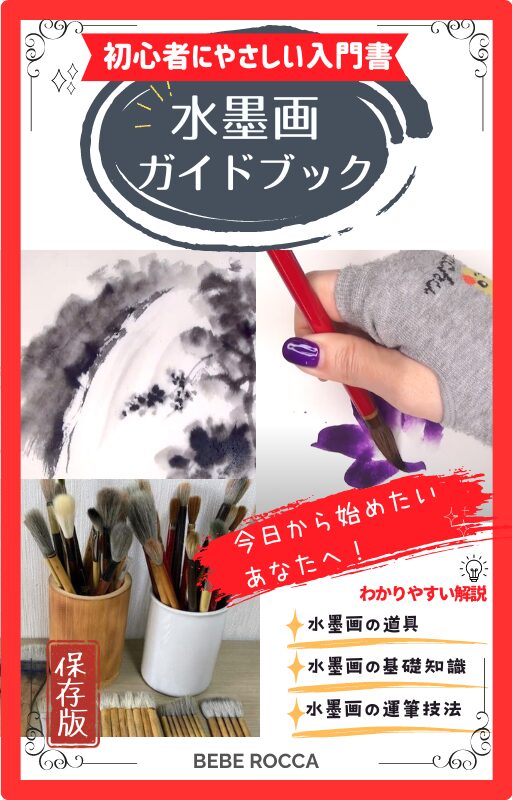
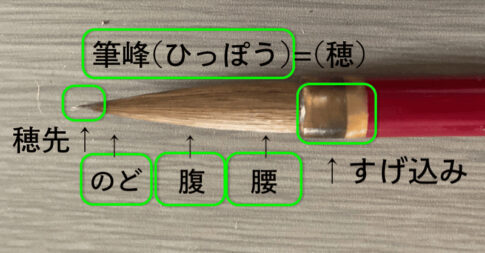






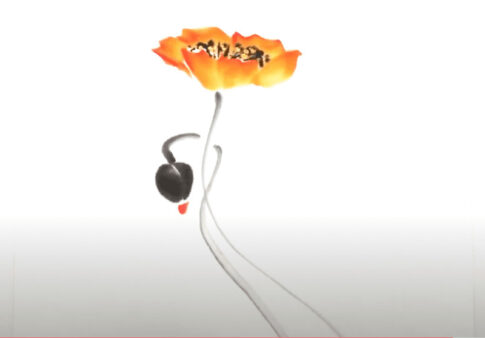


水墨画の基礎が簡単に学べる『電子書籍』
『レッスン講座動画』
無料プレゼント中!
「水墨画を基礎から学びたい」
「絵を生涯の趣味にしたい」
「本格的な水墨画を描きたい」
そんな方のために作った、電子書籍と水墨画が学べるビデオ講座を無料プレゼント中です。
水墨画の基礎知識や道具についてなど、初めて筆を取る方にも優しい入門書となっていますので、ぜひご覧ください。